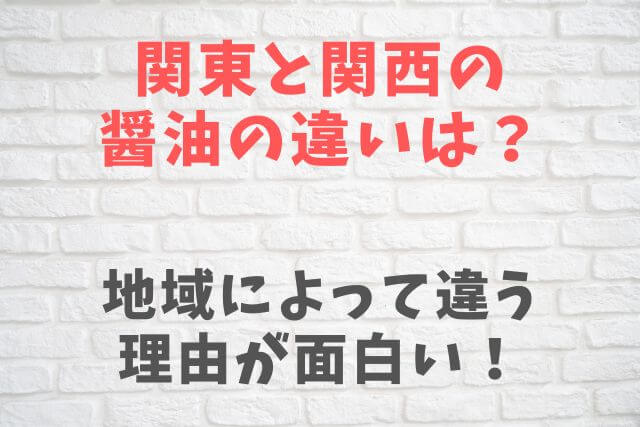どこの食卓にも置いてある調味料の1つに、醤油がありますよね。
それぞれの家庭の味があるように、醤油の好みもさまざまだと思います。
スーパーに行くといろいろな醤油が売られていますが、一般的に関東と関西では醤油に違いがあります。
その違いとは?
また、なぜ地域によって食文化に違いがあるのかも気になりますね。
そこで今回は、
- 関東と関西の醤油の違いは?
- 地域によって食文化が違う理由が面白い!
について、お伝えしていきます。
関東の醤油は関西と何が違う?
日本一広大な関東平野を悠々と流れる利根川水系、土中のミネラル分(Ca,Mg)を溶かし込む。この中硬水は昆布出汁を取るには不向きだが、酵母を活性化し力強い濃口醤油を生んだ。軟水関西では薄口醤油。私見だが関東醤油文化の最高傑作は、味わい深い蕎麦つゆと内湾東京湾穴子煮のツメ添え。#美食地質学 pic.twitter.com/1BKzX8UTtK
— 巽好幸 (@VolcanoMagma) February 7, 2021
醤油にもいろいろな種類があります。
関東で主流の醤油とはどのような醤油なのでしょうか。
関東で使用されている醤油は、主に濃口醤油です。
濃口醤油は色が濃く、うま味もしっかりきかせた醤油ですね。
しっかりと味をつけたい煮込み料理や炒め物に適しています。
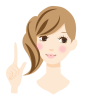
辛い系が続いて、やはりここに戻るw
関東の醤油ラーメン🍜
もう毎日これでいいんじゃね?🙄
いつどんな時でも美味しい✨
間違いなし❣️普通が一番😂 pic.twitter.com/XNTUsfmqV9
— ユリア (@1107yuria) February 18, 2022
そばよし@京橋店さん。かき揚げそば490円
至高の鰹の効いた出汁と茹でたてそばをオフィスから徒歩でありつける喜びをかみしめて、残り少ない関東そばライフを楽しみます。#路麺 #立ち食いそば pic.twitter.com/u1MvubSOK1
— シン・泥酔部長 (@masatosi05) May 29, 2023
濃口醤油がベースのラーメンやそばは、やはりスープも黒いです。
関東の味に慣れた人は、これじゃないと物足りないでしょうね。
関西の醤油は関東と何が違う?
龍野は今でも関西の醤油産地♪ pic.twitter.com/OZyMJowWXp
— くまおやじ本垢❣️٩( ᐛ )و🤳 (@d255477X) August 16, 2022
関東は濃口醤油が主流なのに対して、関西では淡口醤油が好まれています。
淡口醤油は色が薄く、香りも少なめです。
ですから、食材本来のうまみを引き立てることができ上品に仕上がります。
本場の関西うどん。
投入。 pic.twitter.com/OSoAtgIVpr— 夜を駆ける猫村 (@alc_nekomura) April 30, 2023
#昼ご飯 #ランチタイム #社員食堂 #たぬきそば #そば #サラメシ
今日の昼ご飯、火・木は麺の日と言う事で、社食のたぬきそば(関西風出汁/¥174)✨ pic.twitter.com/bA2iX5EyI2— MG☁AIMの父@料理のお父さん🍳🔪 (@AIM21226757) June 13, 2023
淡口醤油がベースだと、スープの色も関東に比べると薄いですね。
上品な感じがします。
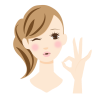
では、なぜこのように地域によって食文化が違うのでしょうか?
その理由について、次にお伝えしていきますね。
関東と関西の食文化が違う理由は?

そもそも関東と関西で味が違うのはなぜなのでしょうか。
その理由は、江戸時代までさかのぼります。
江戸時代以降の日本の中心は、京都や大阪など関西でした。
京都では昆布などのだし文化が発達していたので、素材そのもののうま味とだしで楽しむのが基本。
そのころは中心であった関西に比べて、関東地区は未開発の湿地が広がる荒地だったそうです。
そんな江戸に、時の権力者である豊臣秀吉により移行させられたのが徳川家康だったのです。
徳川家康は、さっそく江戸の町の整備に取り掛かりますが、必要なのは、やはり労働力。
少しでも効率よく働かせるために徳川家康が考えたのが、ごはんがすすむ味の濃いおかずでした。
特に夏場は塩分補給も必要です。
濃いおかずであれば、塩分も摂取することができますもんね。
味の濃いおかずは江戸の一般家庭の食事でも食べられるようになり、関東には濃い味が定着していきます。
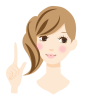
こうして関西は素材のうまみを味わう薄味・関東は濃い味と異なった文化になったそうですよ。
関東が濃い味になったのが、徳川家康の労働力を高めるための知恵とは、面白いですね!
まとめ
今回は、
- 関東と関西の醤油の違いは?
- 地域によって食文化が違う理由が面白い!
について、お伝えしてきました。
関東と関西の醤油の違いは、濃口と淡口の違いです。
関東が濃い味付けになったのは、徳川家康が労働力を高めるための戦略でした。
遠い歴史上の人物だと思っていた徳川家康によって、関東と関西の食文化の違いが生まれたというのは、面白いですね。